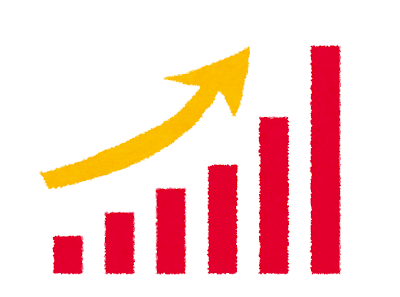
突然ですが、ここ2,3年で様々な価格が大幅に上がっているのを感じます。
スーパー行っても、特売で100円を切る価格だった野菜も3桁が当たり前。98円で「すげー安い!」と思うようになってきていて、それなりに身近なところにも価格上昇が浸透しつつあるような気がしております。
かくいうわかやまNPOセンターも物価高騰のあおりを様々なところで受けています。
指定管理者として運営をお預かりしている和歌山県NPOサポートセンターでは、共益費が1割上がり、電気代も大幅に上がり、各種消耗品の調達価格も少しずつ上がっています。ご利用のみなさんには申し訳ないのですが、印刷機や長尺プリンタは資材の原価ベースでご利用いただいていますので、物価が上がるとご利用料金も少しずつ上げざるを得ないという状況が続いています。
もっとも、このような形で少しずつ物価が上がっていくと、市場に流通するお金も少しずつ上がっていき、ひいては働く人の賃金の上昇に反映される…はずですので、ある程度は苦しいながらも受け入れざるを得ないと思っています。
ただ、そこに住まう人が減少していく地域では、そもそものパイが少しずつ減少していくわけで、しまいに厳しい状況に陥ってしまうのかもしれないという懸念もなくはありません。
また、単年度の事業を行政機関から受託している団体さんにうかがうと、行政事業の委託費はなかなか変わらず、前年度同額が関の山。そこで働く人の賃金アップに反映させたくても困難、また最低賃金が年々上がると人件費割合が上がり続けることになり、肝心の事業費に十分な費用を回せないというネックもあるようです。一応、国としては物価が上がった場合は委託費にも反映させるようにという趣旨の通達は出しているようなのですが、なかなかうまくはいっていないよう。
物価高騰に順応していければいいのですが、物価高騰に抗うように事業展開をせざるを得ない場合は柔軟な収入確保を認める・求める試みも必要なのかもしれません。
しかし、いったいお金はどこにあるんでしょうかねぇ。
